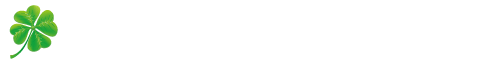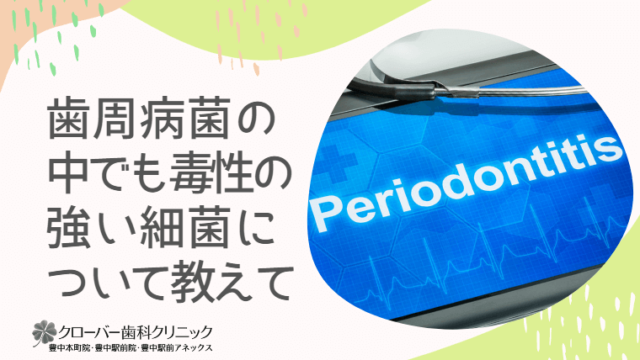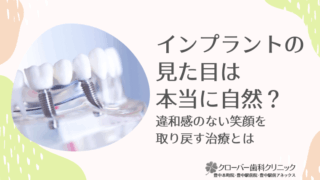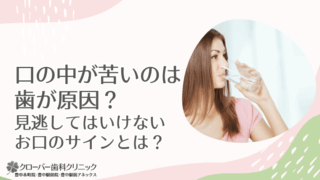4mmの歯周ポケットは治る?進行を防ぐために知っておきたい治療とケア
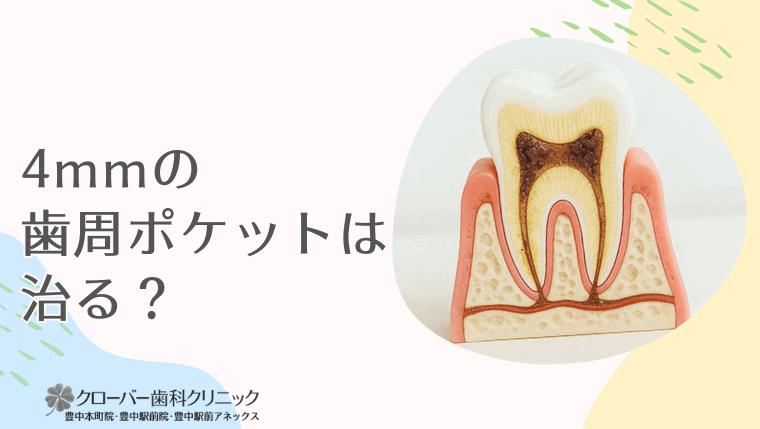
「歯ぐきのポケットが4mmって言われたけど、これって大丈夫なの…?」
そんな不安を抱えながら、鏡の前でお口の中をじっと見つめているあなたへ。
歯周ポケットの深さは、歯周病の進行度を示す大切なサインです。特に「4mm」と言われると、軽度の段階なのか、それとももう深刻なのか…判断に迷いますよね。
この記事では、
- 4mmの歯周ポケットは治るのか?
- どんな治療が必要なのか?
- 自分でできるケアはあるのか?
など、患者さんが知っておきたい情報をやさしく、わかりやすく解説していきます。
「まだ大丈夫」と放置せず、今できる対処を知って、未来の歯ぐきを守りましょう。
目次
4mmの歯周ポケットは治るの?結論から言うと…
4mmの歯周ポケットは、初期の歯周病が疑われる状態ですが、早期に適切な治療とセルフケアを行えば、状態を改善し健康な歯ぐきに近づけることが可能です。ただし「完全に治る」ではなく、「改善して再発を防ぐ」ことが目標です。
4mmの歯周ポケットは早期治療で改善が可能です。
4mmのポケットとは?
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ポケットの深さ | 4mm(やや深い状態) |
| 歯ぐきの状態 | 炎症が見られる可能性あり。赤みや腫れが出ている場合も |
| 歯周病の進行度 | 軽度〜中等度の歯周病が疑われる段階 |
| 自覚症状の有無 | まだ無症状のことも多いが、歯ぐきからの出血や口臭などが出ることも |
| 歯磨きの注意点 | 歯と歯ぐきの境目を意識して、やさしく丁寧に歯磨き。デンタルフロスの併用がおすすめ |
| 治療・対応方法 | 定期的な歯科でのクリーニング、歯周基本治療(スケーリング・ルートプレーニング)など |
| 放置した場合のリスク | ポケットがさらに深くなり、歯を支える骨が破壊されて歯がグラグラする可能性 |
なぜ4mmになると注意が必要なのか?
健康な歯ぐきのポケットの深さは1~3mmが理想です。4mmを超えると、歯垢や歯石がポケットの奥にたまりやすくなり、炎症が進行しやすくなります。そのまま放置すると、歯を支える骨にダメージが及び、歯周病が進行します。
4mmは歯周病の初期段階。放置すると進行します。
4mmのポケットの注意点
歯垢がたまりやすい
→ 歯ブラシが届きにくく、歯垢が蓄積されやすい状態です。
炎症が悪化しやすい
→ ポケット内の細菌により、歯ぐきの炎症が慢性化しやすくなります。
骨に影響が出る可能性
→ 歯を支える骨にまで炎症が及ぶと、後戻りが難しくなります。
4mmは、見過ごされがちですが「進行手前のサイン」。しっかりと対策をとることで深刻な歯周病への進行を防げます。
4mmの歯周ポケットに行う基本的な治療法
歯科医院では、スケーリングやルートプレーニングといった処置が行われます。これにより歯垢や歯石、炎症の原因菌を除去し、歯ぐきの状態を改善していきます。重症でなければ、外科的処置は不要な場合がほとんどです。
スケーリングとルートプレーニングで改善が期待できます。
主な治療内容
- スケーリング(歯石除去)
歯ぐきの上・下に付着した歯石を専用の器具で除去。 - ルートプレーニング
歯の根の表面をなめらかにし、歯垢の再付着を防ぎます。 - ポケットの検査・モニタリング
継続的にポケットの深さを測定して改善度を確認します。
4mmであれば、比較的シンプルな処置で済むケースが多いです。ただし、定期的な経過観察と日々のケアの継続が大切です。
自宅でできるケアで改善をサポートしよう
歯科医院での治療に加えて、患者さん自身のセルフケアが回復への鍵です。正しい歯磨きと、補助的なケア(デンタルフロスや歯間ブラシなど)を続けることで、ポケットの改善や再発予防につながります。
毎日の丁寧な歯磨きが改善と予防の基本です。
おすすめセルフケア
- 正しい歯磨き法の習得
→ 歯と歯ぐきの境目を意識して丁寧に磨きます。 - デンタルフロス・歯間ブラシの活用
→ 歯と歯の間の歯垢を除去し、ポケットの悪化を防ぎます。 - マウスウォッシュの併用
→ 抗菌作用のある洗口液で、細菌の繁殖を抑えます。
自宅でのケアを「治療の延長」としてとらえることが大切です。日々の積み重ねが、歯周ポケットの回復に直結します。
再発を防ぐために歯科でできることとは?

歯周病の再発を防ぐには、セルフケアだけでは不十分。歯科医院でのプロフェッショナルケアを継続的に受けることで、歯周ポケットの状態を管理し、悪化を防ぐことができます。定期的な通院と正しい指導が、長期的な健康維持のカギになります。
歯周病の再発防止には、定期的な歯科でのプロケアが欠かせません。
再発を防ぐために歯科で行える具体的な対策
1. 歯周基本治療(スケーリング・ルートプレーニング)
- スケーリング
歯の表面や歯周ポケット内にたまった歯石・歯垢を、専用の器具で丁寧に取り除きます。
→ 毎日の歯磨きでは取りきれない汚れを除去できます。 - ルートプレーニング
歯の根の表面を滑らかにして、歯垢や細菌の再付着を防止します。
→ 歯ぐきが再び歯にしっかりと付着しやすくなります。
これらは、歯周病の再発を「根本から予防」するための基礎的な治療です。
2. 定期的なメンテナンス(SPT:Supportive Periodontal Therapy)
- 歯周治療後、歯ぐきやポケットの状態を長期的に維持管理するための通院プログラムです。
- 通院間隔は人によって異なりますが、3〜6ヶ月ごとが目安。
- 毎回、ポケットの深さ測定や歯石除去、歯磨き指導などを行います。
「治す治療」から「守る治療」へ切り替えることが、再発を防ぐカギになります!
3. プロによるセルフケア指導
- 歯磨きの当て方、磨き残しのチェック
- デンタルフロスや歯間ブラシの正しい使い方
- ライフスタイルに合った口腔ケアアドバイス
「ちゃんと磨いてるつもり」でも、歯周病の再発は“磨けてない”が原因のことが多いです。
4. 噛み合わせや被せ物の調整
- 歯周病が進むと、噛み合わせが変化しやすくなります。
- 不正咬合や合わない被せ物が、一部の歯に過剰な負担をかけてしまい、再発の原因に。
歯科で調整を受けることで、全体のバランスが保たれ、歯周組織の負担を軽減できます。
5. リスク因子(喫煙・糖尿病など)へのアプローチ
- 喫煙者は非喫煙者に比べ、歯周病の再発リスクが2倍以上。
- 糖尿病も、血糖値が安定しないと歯周組織が治りにくいため、連携医療が必要です。
歯科では、これらのリスクに対して医科との連携や生活習慣改善のアドバイスも行っています。
歯科の力を借りて「再発させないお口」へ
歯周病は一度治しても、油断すれば再発しやすい“慢性疾患”です。だからこそ、セルフケア+歯科でのプロケアの“二刀流”で守ることが大切。
そして、歯科は「治す場所」だけじゃなく、「守るパートナー」として使っていいんです。気になることがあれば、何でも相談してくださいね!
早めの対処がカギ!放置することで起きるリスクとは
4mmの歯周ポケットを放置すると、やがて5mm、6mmと悪化し、歯を支える骨の破壊が進みます。最悪の場合、歯を失う可能性もあります。「まだ痛くないから大丈夫」と思わず、早めの診断・治療が重要です。
放置は危険。進行すると歯の喪失につながります。
放置によるリスク
ポケットのさらなる拡大
→ 炎症が進み、より深い歯周ポケットへと進行。
歯のぐらつき・脱落
→ 支えとなる骨が溶け、歯を失うリスクが高まります。
全身疾患との関連
→ 糖尿病や心疾患などとの相関も報告されています。
今は軽度でも、時間が経つほど治療が難しくなります。気づいたときの行動が、将来の健康を守る第一歩です。
まとめ
4mmの歯周ポケットは、「治らない」わけではありません。適切な治療とケアによって改善することは可能です。ただし、自然に元通りになることは少なく、放置すれば悪化するリスクが高まります。
だからこそ、早期の歯科受診と継続的なセルフケアがとても大切。
一緒に、健やかな歯ぐきを目指しましょう。