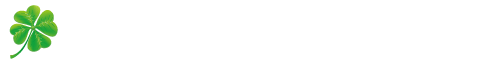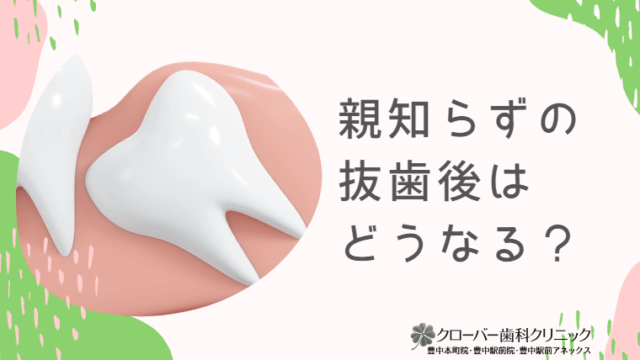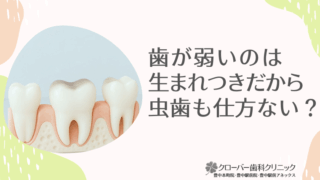歯にいい食べ物とは?栄養で守る健康な歯の作り方

歯にいい食べ物があるならば詳しく知りたいと思われるのではないでしょうか。歯に良い食べ物とは、カルシウム、リン、ビタミンA、ビタミンC、ビタミンD、マグネシウム、フッ素などが含まれた食べ物です。しっかり栄養を摂取し、よく噛んでいると、永久歯を健康に保て、高齢になった際に認知症などにかかりにくくなります。歯にいい食べ物や飲み物、反対に良くない食べ物や飲み物についても詳しくご紹介いたします。
目次
なぜ歯にいい食べ物が重要なのか
食べ物は歯に直接触れるため、エナメル質や象牙質への影響が大きいです。歯は一度削れたり溶けたりすると体の中でも再生力が非常に弱い組織です。そのため、日々の食生活によって歯を強く保つこと、虫歯や歯周病を防ぐことがとても大切です。一度エナメル質が傷ついてしまったり、歯そのものが損なわれると、完全に元に戻すのは難しく、歯科での処置や治療が必要となります。
毎日の食事から歯にいい食べ物を意識して取り入れることが、虫歯や歯周病の予防、歯の老化抑制にもつながります。栄養素は歯や歯ぐきの修復及び保護機能を助け、咀嚼は唾液分泌を促すため口内を中性化し、汚れを流すことができます。つまり、歯にいい食べ物とは、ただ健康な食べ物を選ぶだけではなく、歯そのものを守るという観点からも選ぶべきです。
歯を強く保つための必須栄養素
歯とその周辺組織を守るためには、カルシウムやビタミン、リンなどの栄養素をバランスよく摂取することが鍵です。これらを偏らずに満遍なく摂取することで、歯そのものの強度を高めつつ、歯ぐきや歯槽骨などの歯周組織も健康に保つことが期待できます。
| 栄養素 | 主な働き | 多く含まれる食品 |
|---|---|---|
| カルシウム | エナメル質や骨の主成分、再石灰化の材料 | 牛乳、ヨーグルト、チーズ、小魚、豆腐、海藻類 |
| リン | カルシウムと結びついて硬さや構造を安定化 | 魚介類、肉、卵、乳製品 |
| ビタミンD | 腸からのカルシウム吸収を助ける | 鮭、鯖、きのこ、卵黄 |
| ビタミンA | 歯や口腔粘膜を保護 | にんじん、かぼちゃ、ほうれん草、レバー |
| ビタミンC | 歯ぐきや歯肉の健康維持、コラーゲン合成を助ける | ブロッコリー、柑橘類、パプリカ、キウイ |
| マグネシウム | カルシウムとリンの代謝調整 | ナッツ類、海藻、緑黄色野菜 |
| フッ素 | エナメル質強化、再石灰化促進、酸の産生抑制 | 緑茶、海藻類 |
日常で取り入れやすい歯にいい食べ物一覧
実践しやすい歯にいい食べ物を、目的別にいくつか紹介します。これらをバランスよく摂取することで、虫歯になりにくく強い歯質を保つことができます。
カルシウム・リンの多い食べ物
- 無糖タイプの牛乳、ヨーグルト、チーズ
- しらす、いわしなど骨ごと食べられる小魚や小エビ
- 豆腐、厚揚げ、納豆などの豆製品
- ひじき、わかめ、昆布などの海藻類
ビタミンA・C補給に役立つ食べ物
ビタミンA・にんじん、かぼちゃ、ほうれん草、レバーなど
ビタミンC・ブロッコリー、パプリカ、柑橘類、キウイ、ピーマン
ビタミンD・骨強化サポート食べ物
ビタミンD・鮭、サバなど
脂溶性ビタミンD3・卵黄
ビタミンD2・干しシイタケ、日光に当てたしめじなどのきのこ類
マグネシウム・繊維重視の食べ物
- アーモンド、くるみなどのナッツ類
- ほうれん草やえだまめ、あおさのり
フッ素を含む食べ物
- エナメル質を強化し、虫歯菌の酸に強い歯を作る緑茶や海藻、みかん
清掃性や噛む刺激をもたらす食べ物
- にんじん、ごぼうなどの根菜類、セロリなどの繊維質な野菜
- 適度な硬さと繊維のあるりんご
- 唾液を促す酸味のある梅干しなど
- 玄米や雑穀米などの歯ごたえのある穀物
これらを日々の献立に取り入れることで、無理なく歯にいい食べ物を摂りやすくなります。
歯にいい飲み物、口内環境を整える飲料
飲み物も口腔内の環境に直接影響します。
- 食後にお口の中を洗い流し、酸性環境を中和する水
- カルシウムとリンが補給できる栄養がある無糖の牛乳
- カテキンを含み、抗菌作用も期待できる緑茶
食べ方や習慣で差がつく歯を守る取り組み
ただ、歯にいい食べ物を選ぶのみではなく、摂取の仕方もポイントです。どう食べるか、いつ食べるかであったり、食後のケアも重要です。
食事時間を決める
だらだら食べ続けると口腔内が常に酸性になった状態になり、歯が再石灰化する時間が取れません。間食を減らし、食事の回数や時間を規則的にしましょう。
よく噛むことを意識する
咀嚼を増やすことは唾液の分泌を促進します。口腔内の自浄作用となり、酸を中和する作用が高まります。硬さや食感のある野菜や穀物を取り入れるのが効果的です。
食後すぐの歯磨きは注意
食後すぐに強く磨くと、酸で軟化したエナメル質を傷つける可能性があります。目安としては食後30分から1時間ほど時間をおいてから磨くのが望ましいです。
食後のうがいや水分補給
食後に口をすすぐことで、糖分や酸性物質、食べかすを洗い流し、口腔内の環境を中和しやすくします。また、水分補給を怠ると、お口の中が乾燥し、細菌が繁殖しやすくなるため、こまめな水分補給を心掛けましょう。
就寝前の飲食を控える
就寝中は唾液の分泌が低下するため、口内が乾燥して細菌が繁殖しやすくなります。寝る前の飲食はなるべく避け、甘いものや酸性の飲料は控えましょう。
要注意!歯に悪い食べ物や飲み物
歯にいい食材と並行して、反対に歯に悪い食品や注意したい飲料を知っておくことも大切です。
歯に悪い食べ物と特徴
| 特徴 | 食べ物 | 歯への悪影響の理由 |
|---|---|---|
| 糖分が高く残りやすい | キャンディ、キャラメル、チョコレート、グミ | 口の中に長く残り、虫歯菌が酸を作りやすく、唾液で洗い流しにくい |
| 酸性が強い | レモン、グレープフルーツなどの柑橘類 | 強い酸がエナメル質を溶かし、知覚過敏や虫歯のリスクを高める |
| べたつき・くっつきやすい | 餅、ドライフルーツ、菓子パン | 歯の表面や隙間に残りやすく、長時間虫歯菌の栄養源となる |
| 硬すぎる | 氷、飴、殻ごと無理に噛むナッツ | 歯に強い力が加わり、欠けやヒビ、詰め物の破損などの原因になる |
控えた方がいい飲み物
| 特徴 | 飲み物 | 歯への悪影響の理由 |
|---|---|---|
| 強い酸性の飲料 | 炭酸飲料、エナジードリンク、酢の飲料 | 酸性度が高くエナメル質を溶かすリスク有。それにより知覚過敏や摩耗の原因となる |
| 糖分を多く含む飲料 | 甘いジュース、清涼飲料水、スポーツドリンク | 糖分が虫歯菌のエサとなり、酸を産生して虫歯の原因となる。口の中に糖が残りやすい |
| 着色成分を含む飲料 | コーヒー、紅茶、赤ワイン、コーラなど | ポリフェノールやタンニンなど着色成分が歯の表面に付着し、ステインの原因になる |
酸性や糖分、着色成分を含む飲み物を飲む際に、ストローを使うと影響を軽減できます。完全に避けるのは難しいですが、摂取頻度を抑えたり、食後にすぐ口をすすいだり、歯磨きを心がけたりすることでリスクを下げられます。特にエナメル質が薄い乳歯の子どもや、加齢で歯茎下がりをしている高齢者、歯並びが悪い人などは注意が必要です。
まとめ

歯にいい食べ物は、ただ体の健康状態を良くするものではなく、歯そのものの強さや維持、予防に直結します。カルシウム・リン・ビタミンA・ビタミンC・ビタミンD・マグネシウム・フッ素などの栄養素のバランスを考え、日常で取り入れやすい乳製品、小魚、緑黄色野菜、ナッツなどを活用しましょう。注意すべき食品、酸性や糖分の高い飲料は控えて、過度な摂取を避け、食生活習慣は規則正しくしてください。よく噛んで食事をして、食後のうがいや時間をおいて歯磨きを行うと、虫歯や歯周病のリスクを軽減でき、長く自分の歯を使える可能性が高まります。