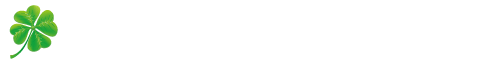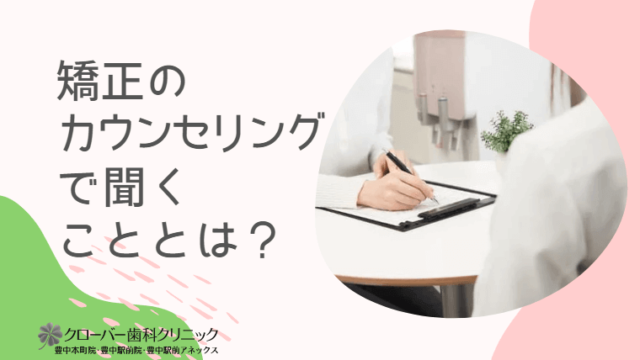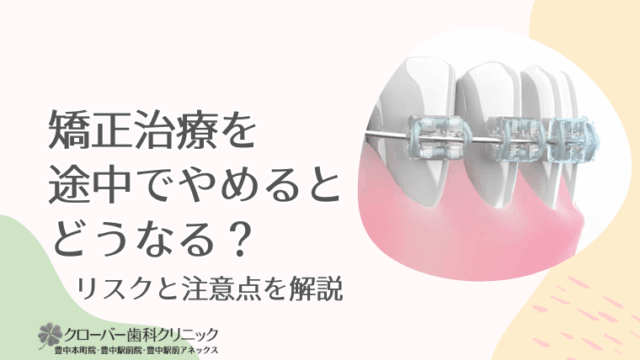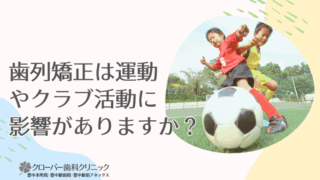下の歯の歯並びが悪いのはどうすれば?
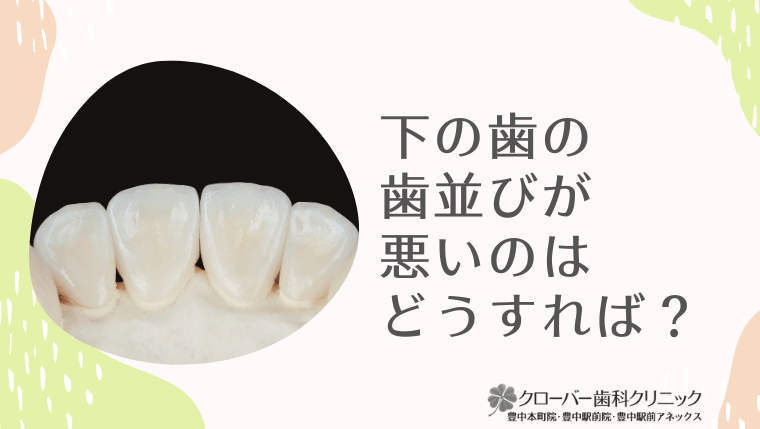
下の歯の歯並びが悪いことに悩んでいる方も少なくはありません。一般的に歯並びが悪いというと上の前歯のガタつきをイメージする方が多いですが、下の前歯の歯並びは歯のサイズに対して顎の幅が足りないことが多く、歯が重なり合って生えてしまったり、歯列が凸凹になったりします。詳しく説明していきましょう。
下の歯の歯並びが悪いとはどんな状態
歯並びが悪い状態を専門的に不正咬合と呼びます。下の歯並びに起きやすい不正咬合は、歯列の並びが悪い叢生(そうせい)や、受け口と呼ばれる反対咬合が考えられます。
歯が重なって生えている叢生
歯のガタガタや、乱ぐい歯と一般的に呼ばれることが多いです。歯磨きがしづらくなることで汚れが溜まりやすく、虫歯や歯周病のリスクが高まります。また、歯並びがガタガタになると、見た目にコンプレックスを感じることもあります。さらに、噛み合わせが乱れると顎に負担がかかり、顎関節症の原因になることもあります。
下の前歯が上の歯より前方に出ている反対咬合
通常と異なり下の歯が前に出る噛み合わせになっている状態を、受け口と一般的に呼ばれることが多いです。発音がしにくかったり、食事の際に噛みづらさを感じ、顎の骨に負担がかかり顔の輪郭に影響が出ることもあります。噛む力のバランスが崩れることで消化不良となりやすく、健康面でも注意しなければなりません。
下の歯の歯並びの乱れは見た目の問題だけでなく、機能的な問題や健康リスクが高まるため、早めの理解と対処が大切です。
下の歯の歯並びが悪くなる原因
下の歯の歯並びが悪いのには、遺伝的要因や顎の発達不足などいくつか考えられます。
遺伝的要因
顎の大きさや歯のサイズは親から受け継ぐことが多いです。同じような歯や顎のお悩みがある方が近くにいると、どうしても先天的な遺伝が起きやすいです。顎が小さいのに歯が大きければ、歯が並びきれずどうしてもガタガタになります。
顎の発達不足
前歯でちぎり奥歯でしっかりとすりつぶすという咀嚼を日々行っていなければ、顎の発達には繋がりません。幼少期の食生活がやわらかいものに偏ると、発達が不十分な顎では、歯の並ぶスペースが不足します。
歯の生え変わりの問題
永久歯は顎の中で歯杯(しはい)という状態で成長していきます。ある程度歯胚が成長すると、破骨(はこつ)細胞が乳歯の根を溶かし、乳歯が抜け永久歯が生えてきます。ところが乳歯がなかなか抜けないと、永久歯が正しい位置に生えられず、別の部分から生えてしまい、歯並びの乱れを起こしてしまいます。
生活習慣や舌の癖
生活習慣や舌の癖は、顎に大きく影響を与えます。
- 舌で下の歯を押す
- 爪を噛む
- 頬杖をつく
- うつぶせ寝
- 歯ぎしりや食いしばり
- 口呼吸
いずれも過度な力がかかると、どうしても筋肉の左右差に繋がり、不正咬合が起きたり、顔貌に影響が出ることがあります。
親知らずの影響
下顎の一番奥に遅く生える親知らずは大きな奥歯です。ある程度のスペースがなければ、前方の歯を押してしまいます。下の前歯がガタガタになることもあります。
要因が複合的に作用し、下の歯の歯並びが悪い状態を作り出します。
下の歯の歯並びが悪いことで起こる影響
下の歯の歯並びの乱れは、見た目の印象に影響するだけでなく、噛み合わせの不具合や、虫歯のリスクなどさまざまなトラブルを引き起こします。
| 影響 | 内容 |
|---|---|
| 見た目のコンプレックス | 歯並びの凸凹が笑顔の際に目立ち、自信を失う原因になる。 |
| 噛み合わせの不具合 | 上下が正しく噛み合わず、前歯で食べ物を噛み切りにくい。 |
| 虫歯・歯周病リスク | 歯ブラシが届きにくく、歯垢が溜まり、虫歯や歯周病になりやすい。 |
| 発音のしにくさ | 歯並びや受け口が原因でサ行・タ行が発音しづらく、滑舌が悪くなる。 |
| 顎や全身への影響 | 噛み合わせのズレが顎関節に負担をかけ、頭痛や肩こりの原因になる。 |
見た目のコンプレックス
下の歯が凸凹した状態では、笑ったり口を開けた際に周囲の人に見え、ご自身が気にして悩みになることが多いです。悩みが深くなるとコンプレックスになり、自信を失う原因につながります。
噛み合わせの不具合
上顎が正しい歯並びでも、下顎の歯並びが悪いとどうしても正しく噛み合いません。食べ物をうまく千切るという前歯の役割を果たせず、噛めない、もしくは噛みにくいことがあります。
虫歯や歯周病のリスク増加
歯が重なっている部分は、歯ブラシの毛先も入り込めないほど届きにくいです。歯と歯肉の境目にも正確に毛先が当たらないことが多いです。それらの部分に食べかすや歯垢(プラーク)が溜まりやすく、虫歯のみならず歯周病にもなりやすいです。
発音のしにくさ
下の歯の位置がずれていると、特にサ行やタ行の発音がしにくいです。
- サ行:歯のガタガタに悩む叢生の方は息が漏れる
- タ行:上顎の歯が下顎より内側に悩む受け口の方は、舌を動かしづらく滑舌が悪くなる
顎や全身への影響
噛み合わせのズレは、顎をずらしていることになります。そのため、顎関節に負担をかけ続けてしまい、頭痛や肩こりを引き起こすこともあります。
このように、下の歯の歯並びが悪いことは見た目だけの問題にとどまらず、体の健康に大きく関わります。
放置すると起こるリスクについて
下の歯の歯並びが悪い状態をそのまま放置すると、時間の経過とともにトラブルが大きくなる可能性があります。スペースが少ない中親知らずが生えてしまうと、更に前歯のガタつきは増していきます。
舌や唇の力の低下により歯並び悪化
舌の理想的な位置は、上の前歯の裏側のスポットと呼ばれる部分に舌先が触れている状態です。ところが舌の筋力が低下すると舌が下がり、その結果下の前歯を押して傾けてしまうことがあります。舌と唇の間にある歯は、舌からの内側への力と唇からの外側への力のバランスで位置を保っています。日常的に口が開き唇の筋力が弱いと下の前歯が傾く原因になり、また、口周りの筋肉は加齢とともに衰えるため、歯並びにも悪影響を及ぼします。
歯周病の進行
歯磨きを怠って食べかすや歯垢が残った清掃不良が続くと、唾液の中の成分と結合し、あっという間に歯石になります。歯石は歯周ポケットにも入り込み、セルフケアでは取れず、歯ぐきの腫れを起こしてしまいます。歯周病は静かに進行するサイレントディジーズと呼ばれ、歯肉の腫れや出血を放置すると、膿や歯が揺れ動くなどの自覚症状になり、重度へなることが多いです。
噛み合わせのずれの拡大
上下の歯の噛み合わせが乱れていると、一部の歯に過度な力が集中し、歯根の周りにあるクッションの役割を果たす歯根膜に負担がかかって傷つくことがあります。その結果、歯をしっかり支えられなくなり、グラつきが生じる場合があります。また、パソコンやスマートフォンを長時間使用すると、下を向いた姿勢が続き、無意識のうちに歯を食いしばることが増えます。噛み合わせに問題がある人ほど、この食いしばりの影響が強まりやすく、放置すれば顎関節症や咀嚼障害に発展することがあります。
矯正治療の難易度が上がる
早期に治療すれば比較的簡単に改善できますが、大人になってからでは治療期間が長引き、費用も高額になりやすいです。つまり気になってはいるけど、特に痛みもないからと先延ばしにするのは危険と言えるでしょう。
下の歯の歯並びを改善する方法
下の歯の歯並びが悪いと気になっている方は、改善方法を知っておくことが大切です。
矯正治療
歯並びを改善する治療法で、保険適用外となるケースが多いです。
ワイヤー矯正
歯の表面に付けたブラケットの中にワイヤーを通して歯をしっかり動かせるため、重度のガタつきにも対処可能です。表側に付けると費用は安いですが周囲に矯正治療中と分かります。裏側に付けると、周囲に分かりませんが、ワイヤーを海外で作製するため費用は高いです。ワイヤー矯正は患者さん自身で取り外しができず、食事内容に制限があります。
マウスピース矯正
半透明で目立ちにくいマウスピース(インビザラインなど)を装着して、指示を受けた時期が来たら新しいマウスピースへ交換して歯に矯正力をかけます。目立ちにくいため、矯正治療中と分かりにくいです。患者さん自身で取り外しが可能なため食事の制限もありません。ただし、装着時間が指示より少なければ歯が動かず、治療計画が延びてしまう可能性があります。
部分矯正
下の前歯のみを整える部分的な矯正であれば、短期間で比較的低コストで行えます。ただし、噛み合わせが悪いと言われた方には不向きの治療です。
親知らずの抜歯
親知らずが生えたことによって前歯が乱れたケースでは、親知らずを抜くことで進行を防ぐことができます。
習慣の改善
舌や頬のクセを改善し、口呼吸を鼻呼吸へ習慣化することで、歯並びの悪化を抑えられます。日常的にあいうべ体操を行いましょう。
あいうべ体操とは
あいうべ体操は、口や舌の筋肉を鍛えて口呼吸を鼻呼吸に改善するエクササイズで、1セット10回を目安に毎日3セット行うと予防に効果的です。声を出さなくても動作を繰り返すことが大切です。良い歯並びを保つことは、見た目や噛み合わせだけでなく、高齢者に多いオーラルフレイルの予防にもつながります。
オーラルフレイルとは、口周りの筋力が衰えることで、食べる・飲み込む・話すといった機能が低下し、食べこぼしやむせ、誤嚥(ごえん)のリスクが高まる状態を指します。
やり方
- 「あ」:大きく口を開ける
- 「い」:歯を見せて口を横に広げる
- 「う」:唇を前に突き出す
- 「べ」:舌を下に出す
最初は慣れずに疲れたり筋肉痛になることもありますが、続けることで口周りの筋力が鍛えられ、スムーズにできるようになります。
小児期からの予防
子どものうちに顎を広げる治療や、乳歯の生え変わりの管理をすると、将来的な歯並びの悪化を防ぐことができます。
治療方法は患者さんの年齢や歯の状態、生活スタイルによって最適なものが異なります。気になるならばまず歯科医院で相談することが第一歩です。
まとめ

下の歯の歯並びが悪いと、見た目の問題のみでなく、虫歯や歯周病、発音や噛み合わせなど多方面に影響を与えます。放置すると症状が悪化し、治療の難易度や費用も上がるため、早期に正しい方法で改善すれば、歯の健康はもちろん、笑顔に自信が持てる生活を取り戻せます。
まずは歯科医院で診断を受け、適切な治療法(ワイヤー矯正・マウスピース矯正・部分矯正など)を選んでください。生活習慣や癖を改善して、長期的に美しく健康的な歯並びを維持しましょう。