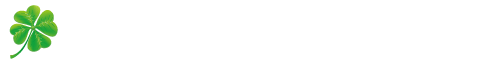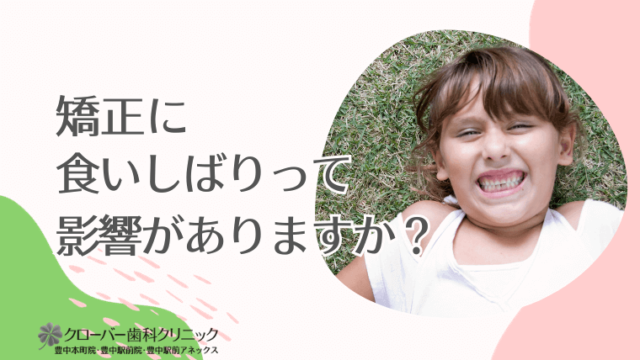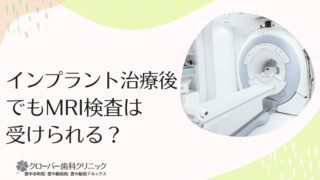矯正で抜歯後の食事とは?正しい食べ方や過ごし方ガイド
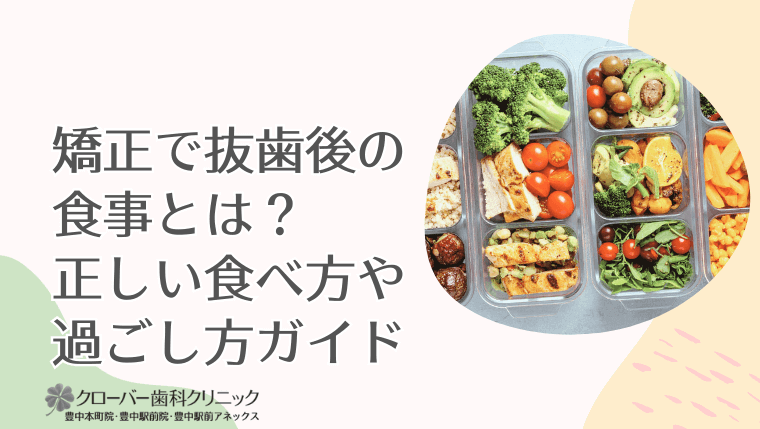
矯正で抜歯後、食事はどうすればよいの?と不安に思うことがあるでしょう。抜歯後の正しい食べ方や過ごし方についても詳しくご紹介いたします。
抜歯直後の食事はOK?
矯正治療の一環として抜歯を行った直後は、口腔内や歯茎、骨の回復がこれから始まるため、食事においても慎重になるべき時期と言えます。麻酔が効いている間は、唇や舌などの感覚が鈍っており、噛んでしまって思わぬケガにつながる可能性があります。抜歯直後の麻酔が切れるまでの時間は食事を控えるべきと指導する歯科医院が一般的に多いです。
止血ができていない段階では、強いうがいやストロー、口を大きく開ける行為などはしてはいけません。抜歯窩(ばっしか)という抜いた歯の穴に、血餅(けっぺい)という血の塊の蓋を形成させにくくしてしまい、回復を遅らせるリスクがあります。
抜歯直後のポイント
この時期における食事のポイントを挙げていきます。
麻酔が切れ、感覚が戻ってから食べるようにしましょう。熱さや痛みを感じにくいため、やけどや噛み締めによる傷口の悪化の可能性があります。
水分摂取は可能ですが、ストローを使うと口内に強い空気の流れが起き、抜歯窩に出血を促す可能性があるため控えましょう。
刺激の強い辛味、酸味、熱すぎる食材や、硬い食材は避け、お口に負担をかけない柔らかい食事を選びましょう。
後の治療をスムーズに進むようにするためにも、注意しておきましょう。
抜歯当日の食事で気をつけること
抜歯をした当日は、抜歯直後の延長線上にあり、さらに注意を要します。抜歯窩が安定しなければ、出血や、腫れ、痛みの可能性が高いため、食事の選び方と体の過ごし方を慎重にしましょう。
激しい運動、長風呂、飲酒など、血行が良くなる行為は避ける
血行が良くなると、抜歯窩の血餅が剥がれてしまいます。抜歯後の骨が口腔内に露出と強い痛みを伴う合併症というドライソケットを引き起こす可能性があります。お風呂に入るのではなく、シャワーで済ませるようにしましょう。
食事は噛みやすくて飲み込みやすいものを
噛みやすく、飲み込みやすく、そして熱すぎないものを選びましょう。抜歯窩への刺激を避けるため、おかゆ、うどん、煮込んだ具沢山スープなどがおすすめです。
食事量や食材の大きさに配慮する
硬めの肉や大きめの野菜などは避け、細かく切る、柔らかく煮るなどの工夫が有効です。
食後のうがいや歯磨きも慎重にする
先述しましたが出血しやすくなるため、抜歯当日は強くうがいせず、優しくゆすぐのが望ましいです。歯磨きで最後に口をすすぐ際も優しく行いましょう。
抜歯当日は口内を休ませて刺激を最小限にし、体の回復モードに寄り添うことがポイントです。
抜歯後1週間以内の食事と過ごし方
抜歯からおおよそ1週間ほどは、歯ぐきや骨、粘膜が治癒していく重要な期間です。矯正治療を進めるためにも、この期間は身体的な負担をかけすぎないように過ごすことが望まれます。ポイントを段階的に整理しましょう。
抜歯直後~3日
出血や腫れが残る可能性があることから、うがいや歯ブラシの毛先が抜歯窩に触れないように配慮しましょう。血餅が剥がれると回復が遅れたり、痛みが長引くためです。
食事はさらに柔らかいものと制限をかけ、噛む、飲み込む負担を軽くします。抜歯した反対側で噛む、食材を小さくする、固さを柔らかくするなどの工夫をしましょう。刺激性のある酢、唐辛子などの辛味や熱すぎる飲食は避けた方がよく、温度や味ともにやさしいものが基本です。
4日~7日目あたり
抜歯窩の回復も進み、おおむね通常の柔らかめの食事に戻す準備ができます。ただし、硬い物や粘着性のある食べ物、噛みちぎるような動きが必要なものはまだ控えめにしておきましょう。
この時期から栄養面にも配慮していき、治癒を促すビタミン、ミネラル、たんぱく質などの栄養素をしっかり摂ることが大切です。抜歯後の矯正装置装着に進む段階になることがありますが、痛みが続いたり出血が止まらない場合は、矯正を始めるタイミングとして歯科医師の判断を仰ぎましょう。この1週間をしっかりケアすることで、矯正治療がスムーズに移行しやすくなります。
傷の回復を促す栄養素と食材選び
抜歯や矯正治療を行った後は、口内や、粘膜、骨や歯ぐきの回復を支えるため、栄養面での配慮も非常に重要です。単に柔らかいものを食べるだけでなく、回復に必要な栄養素を確保することが、長期的な矯正治療を成功へと導くことになります。 注目したい栄養素と食材を挙げます。
| 栄養素 | 働き及び効果 | 多く含まれる食品 |
|---|---|---|
| 亜鉛 | 免疫機能を高め、傷の治りを促進。創傷治癒に関与。 | 大豆製品(豆腐や納豆など)、ナッツ類、牛肉、牡蠣 |
| ビタミンB群 (B2・B6等) |
粘膜の健康維持を助け、口内炎の予防にも効果的。 | 豚肉、納豆、レバー、卵、まぐろ |
| ビタミンC | コラーゲンの合成を助け、歯ぐきや歯槽骨の健康をサポート。 | いちご、キウイ、パプリカ、ブロッコリー、パセリ |
| ビタミンA | 粘膜、皮膚、粘液細胞の再生や成長を促す。 | うなぎ、バター、卵黄、にんじん、かぼちゃ |
食材や調理法の工夫
また、食材や調理法としては次のような工夫がおすすめです。
食材への工夫
食材を小さめに切る、柔らかめに煮込む、もしくは蒸すなどして噛む、飲み込む負担を減らしましょう。お肉、魚、豆類などのたんぱく源をしっかり摂り、硬い赤身肉などは薄切りにし、細かくして調理します。野菜、果物、海藻類などからビタミンやミネラルをバランス良く摂ります。柔らかく調理された野菜スープなども有効です。
アイスクリームやシャーベットなどの冷たいデザートは、痛みがある時期には冷却効果で症状が和らぐ場合がありますが、冷えすぎたり、糖分過多になることもあるので注意しましょう。治癒を促すためには量だけでなく栄養バランスという質も意識して、無理なく食事を続けることがポイントです。
矯正装置装着後の食事の際の注意点
抜歯を終えて矯正治療が本格スタートすると、歯並びを動かすための装置がつくことがあります。装置がついた後も、食事に関しては注意を怠ると治療の進行に影響を及ぼします。
ワイヤー矯正
歯の表面にブラケットという突起を接着し、その中にワイヤーを通して、歯を動かす治療法です。表側に装着すれば矯正治療中と周囲に分かりますし、裏側に装着すると審美性は高いですがその分料金は表側と比べて高くなります。装置の間やブラケットのすき間に食べかすが詰まりやすく、ケアがしにくい矯正装置であるため、虫歯や歯周病リスクも否定できません。
ワイヤー矯正で起こりやすい食事のトラブル
また、硬い食材を勢いよく噛むと、ブラケットの脱離を起こし、ワイヤーの変形の原因になります。ワイヤー矯正では噛みちぎる、硬いものを勢いよく噛むという動作は避けましょう。色の濃いカレーやコーヒー、赤ワインなどの飲食物は装置に付いているゴムが変色するリスクが高く、装置の見た目や衛生面も考慮して、食材や飲料に注意をしなければなりません。
マウスピース型矯正
インビザラインなどのマウスピースを装着し、短期間でマウスピースを交換することで歯を動かす治療法です。担当医の指導より装着時間が少ないと歯の動きが計画通りにならず、再度マウスピース設計をし直すため、費用や治療期間の延長も考えられます。食事前には必ずマウスピースを外す必要があり、装着したまま飲食をすると、変形や変色をし装置の劣化のリスクや、治療が遅延する可能性があります。
マウスピース矯正で起こりやすい食事のトラブル
食事に制限が比較的少ないとはいえ、硬すぎるもの、粘着性のあるものなどは歯や装置に負担となるため、ある程度の工夫は必要です。また、食べかすが歯についたままマウスピースを装着すると、虫歯や歯ぐきのトラブルがワイヤー矯正よりも起きるリスクが高くなります。食後は歯磨き及びうがいをしてから装置を再装着するようにしましょう。
矯正装置を装着している期間は何を食べるかだけでなく、調理法や噛み方、飲み込み方も含めたどう食べるかという点も大切になります。装置トラブルが起きると治療スケジュールが延びる原因となるため、日々の食事習慣にも気を使いましょう。
よくある質問とトラブル回避のためのヒント
矯正治療中、特に抜歯を伴った場合にはこんなときどうすればいいという疑問が湧きやすいです。ここではよくある質問と、それに対するアドバイスをまとめます。
抜歯後どのくらいで普通の食事に戻せるの?
個人差はありますが、抜歯からおおよそ3~7日を目安に、香辛料、酸味などの刺激のある食材、硬さのある食材を徐々に戻していくのが一般的です。3日目以降は、強い刺激を避ければ通常食に近づけるかというところですが、矯正の装置がつくタイミングや、抜歯本数、部位など本人の体調によっても変わるため、担当医の指示を優先してください。
抜歯後食べられない食材は?
抜歯直後~1週間は、今から挙げる食材は外しておくのが賢明です。
- せんべい、ナッツ、固焼きお菓子、フランスパンなど固いもの
- キャラメル、ガム、焼肉の厚切りなど粘着質であったり噛み切りにくいもの
- 辛味、酸味、香辛料たっぷり刺激の強い味付け
- 熱すぎる、反対に冷たすぎるもの
抜歯窩を刺激したり、血餅を剥がしたり、トラブルを起こしたりする可能性がありますので、避けましょう。矯正治療中にも避けた方が良いとは思いますが、どうしてもという場合は担当医に確認をしてください。
どうやって硬い食材を食べられるように工夫すれば?
食材を小さく切り、一口サイズにしたり、蒸したり、柔らかく煮込んでスープにしましょう。硬めの肉や野菜は、細かく刻んだり、ミンチ、ペースト状にして、噛む際はなるべく抜歯した側ではなく、反対側で噛むことを意識しましょう。
抜歯後だけでなく矯正治療中も気をつけるべきことは?
抜歯後の過ごし方が安定していても、矯正治療中の食事習慣が乱れると、装置が外れたり、変形して治療が長引きます。虫歯、歯周病、口内炎など、口腔内のトラブルが起こりやすくなります。ワイヤー、マウスピースなど矯正装置に応じた食事習慣を身につけることが非常に重要です。
痛みや腫れが引かないけど大丈夫?
抜歯後の痛みや腫れは通常、2~3日ほどで落ち着いてくるケースが多いです。出血が30分以上止まらなかったり、抜歯窩が酷く腫れていて化膿したにおいがする、痛みが強くなるなどの症状があれば、すぐに受診しましょう。抜歯後や矯正中のトラブルは、治療スケジュール、結果に大きく影響することから、早めの対処が安心です。
まとめ

矯正治療で抜歯を行った後は、食事、過ごし方、栄養の3本柱で注意を払うことが、スムーズに進めるためには非常に大切です。抜歯直後~当日は刺激を避け、口内を休ませるようにし、1週間以内は柔らかく、噛みやすく、負担の少ない食事を心がけましょう。傷の回復を促すために亜鉛、ビタミン群などを意識した栄養摂取をし、装置を装着後は負担をかけず、食べやすく工夫して調理をしてください。
トラブルが長引くようなら、我慢せず担当医に相談をしましょう。矯正治療は数ヶ月~数年にわたる長期戦になりますが、最初の抜歯後の段階を確実にクリアすることで、その後の治療がより順調になります。食事の工夫ひとつで、痛みや治療期間、仕上がりがより良くなる可能性がありますので、無理のない範囲で毎日の食生活を整えていきましょう。