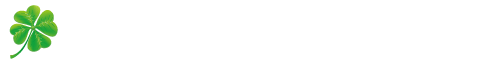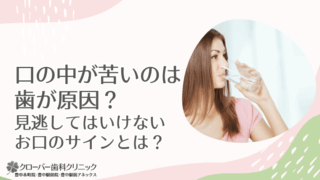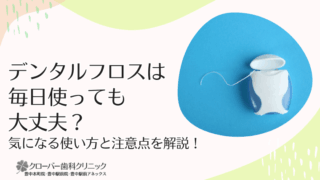歯の痛みと肩こりには関係がある?噛み合わせとの関係にも注目!
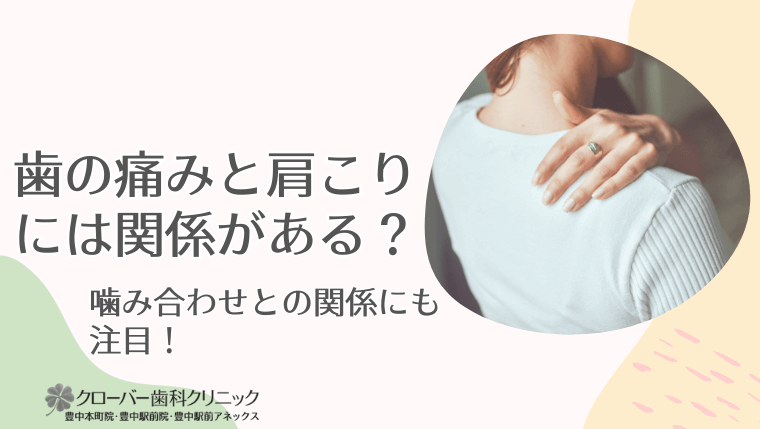
「歯が痛いと肩までこる気がする…」そんな経験はありませんか?
この記事では、「歯の痛みと肩こりには関係があるのか?」という疑問に歯科の視点からお答えします。特に次のような方におすすめの内容です。
- 歯の痛みと肩こりを同時に感じることがある方
- 肩こりが慢性的で、歯にも違和感を感じている方
- 歯科と整形外科、どちらに行けばよいのか迷っている方
答えを先に言うと、歯の痛みと肩こりには関係がある場合があります。
その理由やしくみ、対策を分かりやすくお伝えしていきます。
歯の痛みと肩こりには関連があることがある
歯の痛みと肩こりは、一見無関係に見えても、筋肉や神経のつながりによって関係することがあります。
歯と肩の痛みは連動することがあります。
歯科の分野では、噛み合わせの問題や顎関節のトラブルが、首や肩、背中の筋肉に影響を与えることが知られています。つまり、口の中の状態が全身に波及することがあるのです。
神経のつながりと噛み合わせのバランスが影響している
歯や顎のトラブルが肩こりにつながるのは、神経や筋肉のネットワークが連動しているためです。とくに三叉神経や咀嚼筋のバランスが崩れると、首や肩の筋肉まで緊張が波及することがあります。
噛み合わせや神経の緊張が肩こりに影響します。
歯と肩が「神経」でつながっているしくみ
人間の顔と顎、肩周辺の感覚と動きを支えているのが、「三叉神経」や「顔面神経」「副神経」などの複数の神経ネットワークです。
- 三叉神経(第5脳神経)
→ 歯・顎・側頭部・咀嚼筋に分布しており、痛みの伝達の中心的役割を果たす - 顔面神経(第7脳神経)
→ 表情筋を支配し、感情の緊張やストレスとも密接に関連 - 副神経(第11脳神経)
→ 僧帽筋や胸鎖乳突筋に分布し、首・肩の動きと関係する
これらの神経は頭蓋底(頭の骨の下の部分)や首の深部で交差・連絡しているため、ひとつの部位の緊張が他の部位にも影響を及ぼすのです。
噛み合わせの乱れが筋肉のバランスを崩す
不正咬合や歯の欠損、被せ物の高さのズレなどがあると、咀嚼筋(噛む筋肉)の一部に過剰な負担がかかります。
以下の筋肉が関与しています
- 側頭筋 → こめかみのあたりにあり、咬む動作に関与。緊張が頭痛にもつながる。
- 咬筋 → 頬の奥にあり、強く食いしばる筋肉。緊張すると顎~首~肩へ波及。
- 胸鎖乳突筋・僧帽筋 → 噛み合わせのズレから姿勢が乱れ、これらの筋肉が慢性的にこる原因に。
特に下顎がズレていると、首が傾いたり猫背になったりして、肩や背中の筋肉まで慢性的に負担がかかるようになります。
歯や噛み合わせの問題が肩こりにつながるメカニズム
| 原因となる歯科的トラブル | 関連する筋肉・神経 | 起こりうる症状 |
|---|---|---|
| 不正咬合(噛み合わせのズレ) | 咬筋・側頭筋・胸鎖乳突筋 | 肩こり・首こり・頭痛 |
| 歯ぎしり・食いしばり | 咬筋・側頭筋・三叉神経 | 朝の肩のだるさ・顎の疲労感 |
| 顎関節のずれ・開閉障害 | 顎関節・咀嚼筋群・副神経 | 首筋のこり・姿勢の乱れ |
| 高すぎる被せ物や詰め物 | 咬筋のアンバランスな緊張 | 偏った肩のこり・噛む時の違和感 |
歯ぎしり・食いしばりが引き金になることも
就寝中の歯ぎしりや日中の食いしばりは、無意識のうちに顎周りの筋肉を酷使します。この緊張が肩~首にまで波及し、「原因不明の肩こり」に繋がるケースが多くあります。
歯と肩は“筋肉と神経”でダイレクトにつながっている
歯や噛み合わせの異常が、単に口の中のトラブルで済まず、筋肉と神経の連動を通して首や肩の慢性的なこりにまでつながっているということが、ここでの大きなポイントです。
慢性的な肩こりや首の痛みに悩んでいる方は、「もしかして歯や顎に原因があるかも?」という視点を持つことが、根本的な解決への第一歩になります
不正咬合や歯ぎしりによる肩こりの具体例
不正咬合や歯ぎしりがある患者さんでは、肩こりや頭痛を訴えるケースが少なくありません。噛み合わせの治療によって改善することもあります。
歯並びや歯ぎしりが肩こりの原因になる。
よくあるケース
- 不正咬合が原因で肩に負担がかかっていたケース
→ 上下の歯の接触バランスが悪く、特定の筋肉ばかりを使うため肩の筋肉が凝り固まっていた。 - 睡眠中の歯ぎしりにより咀嚼筋が常に緊張状態に
→ 朝起きると肩や首が重だるいという症状を訴える患者さんもいます。
このような場合、歯科治療と併せて生活習慣の見直しを行うことで、肩こりの症状が改善することがあります。
診療中、「日中無意識に歯を食いしばっていませんか?」と尋ねると、「そういえば…」と気づく方も多いです。歯や顎の不調が、全身の筋肉や姿勢・ストレスなどと密接につながる点は診療現場ならではの肌感覚です。生活習慣やストレスケアも含め、患者さんに合わせた総合アドバイスを心がけています。
歯ぎしりや食いしばりが続く方は、こちらの[歯ぎしり・食いしばりの原因と対策]もぜひチェックしてみてください。
歯科でできる検査と治療法とは?
肩こりが歯や噛み合わせに関係しているかどうかを歯科で検査し、必要に応じてマウスピースや矯正治療を行うことで改善が見込めます。
歯科でも肩こりの原因を探ることができる。
歯科での対応方法
- 噛み合わせチェック
→ 咬合紙などを使い、力のバランスや接触部位を確認します。 - 顎関節の診察
→ 開口量や関節の動き、音の有無などから異常を判断します。 - マウスピースの作製
→ 歯ぎしりや食いしばりがある場合に有効です。 - 矯正治療
→ 不正咬合が原因と判断された場合には、歯並びの改善が必要になることもあります。
歯科医院では、見えない原因までアプローチすることができます。長年の肩こりに悩んでいる方も、一度歯科で相談してみると良いでしょう。
日常生活でできる予防と対策
歯科治療と並行して、日常生活でのセルフケア、姿勢やストレス管理などに気をつけることが肩こり予防に役立ちます。
日常生活の中でも肩こり対策はできる。
日常の予防ポイント
- 正しい姿勢を意識する
→ デスクワーク中に猫背にならないよう気をつけましょう。 - 定期的に口を開閉する運動
→ 軽く顎を動かすことで筋肉の緊張を緩める効果があります。 - ストレスをためない
→ ストレスは食いしばりを引き起こしやすくなります。 - こまめな歯磨きと定期的な健診
→ 虫歯や歯周病による痛みも筋肉の緊張につながります。
こうした習慣を取り入れることで、肩こりの原因を根本から見直すことができます。
まとめ
お口と体のバランスを整えることが大切
歯の痛みと肩こりは、神経や筋肉のつながりを通じて関係することがあります。慢性的な肩こりでお悩みの方は、歯科の視点からも原因を見直してみましょう。
口と体のバランスが、肩こりの改善に重要。
歯と肩がつながっているとは思わなかった方も、今後は「肩こり=歯のトラブルかも?」と視野を広げてみてください。違和感を感じたら、早めの歯科相談をおすすめします。